【企業倒産からの事業再生】
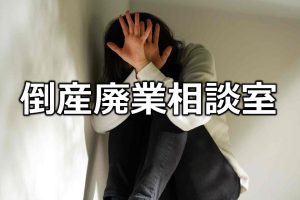
東京商工リサーチによると、2024年の全国企業倒産は10,006件で、前年(8,690件)を15.14%上回り、11年ぶりに1万件を超えました。
アイズルームでは、経営が行き詰った会社経営者のコンサルタントをしております。
経営破綻により命を失う経営者も多く存在しますので、そのような方に寄り添った支援をしております。
「倒産廃業相談室」では秘密厳守で社長様と直接ヒアリングをし、最善の策を提案させて頂きます。最終的には税理士や弁護士とも協議し、社長様の再生に繋がるようにしたいと考えております。
秘密は厳守しますので、こちらをタップしてお問い合わせください。家族や従業員にも話せない事があろうかと思います。
私も40年間企業経営に携わり、成功より大きな失敗を繰り返してきましたが、その都度一文無しからリセットし粘り強く再生してきました。
社長自身が諦めなければ、ゼロからでもやり直しが可能です。
企業倒産からの事業再生は、経営が悪化した企業が倒産を避け、事業を立て直すための重要なプロセスです。日本では、この事業再生を支援するための様々な制度や手法が存在します。
事業再生とは
事業再生とは、何らかの理由で経営状態が悪化し、業績回復が困難になった企業が、経営の建て直しを図ることを指します。単に債務を整理するだけでなく、収益性の改善、事業構造の見直し、組織改革などを行い、企業の持続的な成長を目指します。
事業再生の手法
事業再生の手法は、大きく「法的再生(整理)」と「私的再生(整理)」の2種類に分けられます。
1. 法的再生(整理)
裁判所の関与のもと、法律に基づいて行われる再生手続きです。
- 民事再生法: 主に中小企業を想定していますが、個人や大企業も利用可能です。経営陣を刷新せずに事業を存続させられる点が大きなメリットです。債務の圧縮や弁済期間の延長も可能で、裁判所の監督のもとで公平・公正な手続きが進められます。
- 会社更生法: 大企業向けの制度で、原則として経営陣が交代し、裁判所が選任した管財人が再建業務を行います。民事再生よりも債権者の権利を強く制限できる特徴があります。
- 破産: 事業を清算することを目的とする手続きですが、近年では「プレパッケージ型」と呼ばれる、事業譲渡などによって一部事業を存続させるケースも増えています。
- 特別清算: 株式会社が清算する場合に利用される手続きで、債務超過の際に利用されます。
2. 私的再生(整理)
裁判所を介さず、債権者との話し合いによって進められる再生手続きです。
- 事業再生ADR(裁判外紛争解決手続): 事業再生実務家協会などが公正な第三者として関与し、債務者と金融機関等の間で事業再生計画について合意形成を目指します。非公開で進められるため、企業の信用への影響を抑えやすいメリットがあります。
- 私的整理ガイドライン: 金融機関が共通して適用できる私的整理のルールです。
- 特定調停: 簡易裁判所を介した手続きで、比較的簡易に債権者との合意形成を目指します。
事業再生のメリット・デメリット
メリット
- 企業存続・倒産回避: 会社を消滅させることなく事業を継続できます。
- 雇用の維持: 従業員の雇用を守ることができます。
- 取引関係の維持: 長年の取引先との関係を維持しやすいです。
- 経営権の維持(民事再生の場合): 経営陣を刷新せずに再建を目指せる場合があります。
- 債務の圧縮・弁済期間の延長: 債務の負担を軽減し、計画的な返済が可能になります。
- 社会的な価値の維持: 企業が持つ技術やノウハウ、ブランドなどの社会的な価値を失わずに済みます。
デメリット
- 手続きの複雑さ・時間・費用: 特に法的再生は、手続きが複雑で専門知識が必要であり、時間やコストがかかります。
- 信用の低下: 再生手続きに入ったことが公になると、企業の信用が低下し、新たな取引や金融支援が難しくなる可能性があります(私的再生ではこれを抑えやすい)。
- 資金繰りの厳しさ: 再生計画が順調に進まない場合、資金繰りが好転しないリスクもあります。
- 経営陣の交代(会社更生の場合): 経営権を失う可能性があります。
事業再生を成功させるポイント
- 早期着手: 経営悪化の兆候が見られたら、できるだけ早く対策を講じることが重要です。
- 事業デューデリジェンス: 自社の強み・弱み、収益性の高い事業、不採算事業などを正確に把握し、抜本的な事業構造の見直しを行う必要があります。
- 専門家の活用: 弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士など、事業再生の専門家の支援を受けることが不可欠です。
- ステークホルダーとの協力: 債権者、従業員、取引先など、関係者との信頼関係を構築し、協力を得ることが成功の鍵となります。
- 明確な再生計画: 実現可能性の高い具体的な再生計画を策定し、実行することが求められます。
企業倒産からの事業再生は、困難な道のりですが、適切な手法と専門家のサポートを得ることで、新たなスタートを切るチャンスにもなり得ます。
