【夢と絶望の狭間で—データが語る日本の起業家たちの現実。そして、その先の「再生」への4つの道筋】
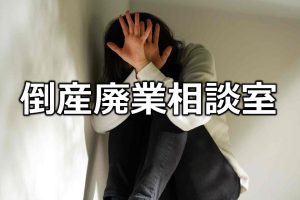
会社を立ち上げる。それは、多くの人にとって人生をかけた夢であり、計り知れない生きがいと情熱をもたらすものです。ゼロから事業を育み、仲間を増やし、社会に価値を届ける。その道は、苦労も多い一方で、何物にも代えがたい達成感に満ちています。しかし、その夢が傾きかけたとき、状況は一変します。周りの信頼から見放され、従業員や家族の心さえも離れていく。起業当初は多くの人が手を貸してくれるのに対し、倒産や廃業という最終的な決断は、経営者がただ一人、孤独に進めなければならない道となります。
特に日本の融資制度では、上場企業でない限り、中小企業の場合、代表者自身が連帯保証人となることが一般的です。そのため、会社の失敗は即ち社長個人の債務となり、欧米のように経営者個人が再起を図ることが容易ではない現実があります。日本では会社の事業失敗が家族の崩壊を招き、最悪のシナリオを選んでしまう経営者も少なくありません。
私自身も、40年間の経営者人生で、ベンチャー企業の立ち上げから東証プライム関連企業の役員まで、誰よりも多くの失敗を重ねてきました。経営が傾き、最悪のシナリオを経験する中で感じたのは、言葉では言い表せないほどの孤独と苦い後悔です。しかし、そのような経験を通して、心底からやり直す気力が残っていれば、人生は決して捨てたものではないという確信を得ました。真摯に失敗を反省し、再起を目指せば、たとえ一人でも手を差し伸べてくれる人が現れ、必ず人生に光が射してきます。
還暦を迎え、グループ企業の代表から退いた今、私の使命はこの苦い経験を活かし、同じような困難に直面している中小企業の支援に当たることにあります。
A. 過去最多を更新した新規法人設立件数
日本経済は、コロナ禍の収束後、起業マインドの高まりを見せています。東京商工リサーチの調査によると、2023年に全国で新しく設立された法人は15万3,405社に達し、統計を開始した2008年以降で過去最多を記録しました 。この増加傾向は続き、2024年の新設法人数はさらに微増して15万3,938社となり、記録を更新しています 。
この起業ブームの背景には、2023年5月の新型コロナウイルス感染症の5類移行による経済活動の本格再開や、政府・金融機関による起業支援策の推進が挙げられます。
B. 夢の後に待ち受ける現実的な壁
新規設立が過去最多を記録する一方で、起業後の事業継続の厳しさも浮き彫りになっています。
一般に広く知られているのは、設立から3年で約65%、10年でわずか約6.3%の企業しか生き残れないという厳しい数字です 。これは、創業からわずか10年で9割近くの会社が廃業していることを意味します。この数字は、廃業・解散を含めたすべての事業終了を対象としているため、経営の難しさをより現実的に映し出しています。
第二部:倒産件数の急増—コロナ禍後の淘汰と複合的要因
A. 負債1000万円以上の企業倒産件数推移
企業が直面する課題は、単に経営努力の問題だけではありません。外部環境の変化が、多くの企業の命運を握っています。東京商工リサーチの調査によると、負債額1000万円以上の法的整理による企業倒産件数は、近年、顕著な増加傾向にあります。
* 2022年: 6,432件、2023年: 8,690件、2024年:1万144件
特に2024年は、東京商工リサーチの年度集計では1万144件に達し、2013年以来11年ぶりに年間倒産件数が1万件を超えました 。この急増は、単一の要因ではなく、複数の複合的な要因が絡み合っていることを示しています。
B. 数字の裏側にある真実—淘汰を加速させる3つの要因
倒産件数増加の背景には、コロナ禍で事業を維持してきた企業が、経済環境の変化に対応できず、限界を迎えているという現実があります。主な要因は以下の3つに分類できます。
* ゼロゼロ(コロナ)融資後倒産
コロナ禍の資金繰り対策として拡充された実質無利子・無担保の「ゼロゼロ融資」は、多くの企業の命を繋ぎましたが、その返済が本格的に始まった現在、多くの企業が資金繰りの見通しを立てられず破綻に至っています。このタイプの倒産件数は過去最多を更新し、中小零細企業の倒産件数全体を押し上げています 。
* 人手不足倒産
深刻な人手不足は、単に採用が難しいという問題に留まりません。従業員の確保ができず事業継続が困難になるケース、人件費の高騰により採算が取れなくなるケースなど、人手不足が直接的な倒産要因となる事案が急増しています。2024年度の「人手不足倒産」は350件と、初めて300件を超え、過去最多を更新しました 。特に従業員10人未満の小規模企業でこの傾向が顕著であり、事業規模が小さい企業ほど、人手不足の構造的な問題に脆弱であることがわかります 。
* 物価高倒産
円安や国際情勢の変動による原材料価格の高騰、エネルギーコストの増加は、多くの企業に影響を与えています。特に、コストを販売価格に転嫁できない中小企業は、利益を圧迫され、経営不振に陥っています。2024年度の「物価高倒産」は925件に達し、過去最多を更新しました 。建設業や製造業、小売業でこの傾向が特に強く、売上があるにもかかわらず利益が出ない、いわゆる「増収減益」が倒産を招いているのです。
これらの要因は、単なる経営不振ではなく、社会構造や世界経済の変化が中小企業に重くのしかかっていることを示しています。倒産は、個人の経営手腕の失敗だけでなく、こうした複合的な外部要因によって引き起こされる、より広範な問題なのです。
事業の継続が困難になったとき、経営者にはいくつかの選択肢が存在します。それぞれの方法には特徴があり、会社の状況や将来の展望に応じて最適な道を選ぶことが重要です。
A. M&A(事業承継・事業譲渡)
M&Aは、もはや大企業だけの話ではありません。中小企業の事業承継や事業再生の手段として広く活用されています。
* 概念と目的: M&Aは、会社を「売る」という行為ではなく、事業のノウハウや従業員の雇用を守り、次の世代に引き継ぐための有効な選択肢です。特に、経営者の高齢化や後継者不在が原因で、本来なら倒産する必要のない「黒字廃業」を避けることができます 。事業承継(会社全体を承継)と事業譲渡(特定の事業のみを譲渡)の2つの手法があり、状況に応じて使い分けることが可能です 。
* メリットとデメリット:
* メリット: 不採算事業を切り離して収益性の高い事業に集中できる 、負債の解消が可能 、従業員の雇用を守れる 、会社のブランドや信用を維持できる 。
* デメリット: 手続きが複雑かつ長期間にわたる 、株主総会の特別決議などが必要で、全株主の同意を得ることが難しい場合がある 、専門家への依頼費用が高額になる場合がある 。
* 手続きと費用: M&Aのプロセスは、M&A仲介業者との相談から始まり、秘密保持契約、トップ面談、基本合意、デューデリジェンス(詳細調査)、最終契約締結、クロージングと進みます 。費用は案件規模に応じて変動する「レーマン方式」による成功報酬が一般的で、そのほか着手金や中間報酬、月額報酬がかかる場合があります 。相談自体は無料の仲介会社も多いですが、着手金は50万~200万円程度が相場とされています 。
B. 債務整理(私的整理・特定調停)
事業の将来性に自信があり、再建を目指す場合、法的整理ではない私的な整理が選択肢となります。
* 概念と目的: 私的整理は、民事再生や破産といった裁判手続きを経ずに、債権者(主に金融機関)との話し合いを通じて債務を整理する非公開の手続きです 。取引先への影響を最小限に抑え、会社の事業価値を毀損することなく再建を図ることを目的とします。特定調停もこの私的整理の一環であり、裁判所が関与して金融機関との利害調整を支援します 。
* メリットとデメリット:
* メリット: 手続きが非公開のため、得意先や仕入先との関係を維持しやすい 。法的整理に比べて費用や時間が抑えられる 。経営者保証に関するガイドラインを活用すれば、連帯保証債務も一体的に整理できる 。
* デメリット: 債権者全員の同意が必要であり、金融機関以外の債権者は対象とならないことが多い 。同意が得られなければ手続きが不調に終わり、結局法的整理に進む必要がある 。
* 手続きと費用: 弁護士や公認会計士などの専門家が仲介役となり、債務者と債権者間の調整を進めます。裁判手続きではないため、裁判所への予納金は不要です。弁護士費用は着手金や月額の報酬が発生しますが、法的整理に比べると負担は少ない傾向にあります 。
C. 自己破産
自己破産は、多額の債務を抱え、事業継続が不可能になった場合の最終的な法的手段です。
* 概念と目的: 会社と経営者個人(連帯保証人である場合)が、法的にすべての債務から解放されることを目的とします。これは事業の「終焉」であると同時に、経営者個人の人生の「再出発」を意味します。日本では、会社と個人が一体と見なされることが多いため、自己破産はしばしば個人債務の問題と切り離せません。
* メリットとデメリット:
* メリット: 法律に基づき債務がすべて免除され、ゼロから再出発できる 。債権者からの取り立てがなくなる。
* デメリット: 会社の資産はすべて清算され、失われる。社会的信用を失い、新たな事業立ち上げや金融取引に制約が生じる場合がある。何よりも、経営者個人の精神的な負担が非常に大きい。
* 手続きと費用: 自己破産には、弁護士費用と裁判所への予納金が必要です。中小企業の場合、弁護士費用は50万円から300万円程度が相場とされています 。さらに、破産管財人への報酬などに充てられる予納金も必要です。通常、負債5000万円未満の法人でも70万円以上の予納金がかかりますが、弁護士が代理人となることで「少額管財」という簡略手続きが適用され、予納金が20万円程度に抑えられる場合があります 。
D. 廃業処理(清算)
倒産とは異なり、事業を自らの意思で計画的に終了させるのが廃業です。
* 概念と目的: 廃業は、債務超過に陥っているわけではなく、事業を継続できる状態にある会社が、将来性への不安、後継者不在、経営者の健康問題といった理由で、自主的に会社を解散・清算することです 。
* メリットとデメリット:
* メリット: 倒産のような負のイメージがなく、円満に事業を終えられる 。取引先や従業員との関係を損なうことなく、会社を畳むことができる。
* デメリット: 会社が清算手続きを完了させるための資金が必要。清算手続き自体に時間と手間がかかる 。
* 手続きと費用: 廃業手続きは、株主総会の特別決議による解散から始まります。清算人を選任し、会社の財産を現金化して債務をすべて弁済した後、残った財産を株主に分配します。そして、清算結了の登記を行うことで会社が正式に消滅します 。費用は、解散・清算人選任登記の登録免許税(3万9,000円)、清算結了登記の登録免許税(2,000円)、官報公告費用(約3万2,000円)などがかかります 。これに加えて、司法書士や税理士への依頼費用が別途発生します。
事業の失敗は、人生の終焉ではありません。それは、新たな一歩を踏み出すための通過点であり、貴重な学びの機会です。
事業の困難に直面したとき、経営者は一人で悩み、孤独を深めがちです。しかし、今日お伝えしたように、事業の立て直しや清算には、法的に、そして現実的に、様々な道筋が存在します。これらの道は、専門家の知見とサポートなしには、非常に複雑で困難なものとなります。
孤独な戦いを続ける必要はありません。あなたが抱えている経営課題は、決してあなた一人の問題ではないのです。再起への第一歩は、その重い荷物を誰かと分かち合うことです。
経営課題に悩んだら、一人で悩むことなくアイズルームにご相談ください。
