【「命綱となる自宅のバリアフリー化へ!」重度障害者向け住宅改修の公的助成を徹底解説!知らなきゃ損する「安全」と「安心」を手に入れる方法】
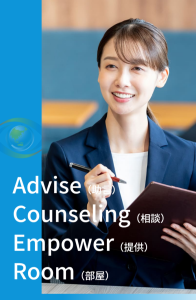
当社の業務は、中小企業の問題解決コンサルタントと、障害者向け就労支援・居住支援のボランティア活動です。
本日の課題は、障害を持った際に不便になる住宅です。健常者の時はさほど問題でなかったところも、いざ障害者になってみると、転倒のリスクがあったり、生活に不自由を感じたりすることがあります。
そこで、地方自治体では、重度な身体障害者(1級・2級)をお持ちの方を主な対象に、住宅改修の助成をしております。
過去にアイズルームでは、関連企業の空家再生高齢者賃貸住宅、公的弱者救済施設、高齢者シェアハウスなどのリノベーションや改修を行ってきました。
以上のような修繕・リフォームの経験を生かして、障害者住宅の公的助成を含めた改善工事を行っております。ここでは、身体障害者手帳1級・2級をお持ちの方を対象とした改修工事についてお知らせします。
【最重要】重度障害者のための住宅改修公的助成制度を徹底解説
障害者の方が安全に暮らせる住宅を確保することは、命と暮らしを守る重要なテーマです。ご自宅の環境を整えるために、地方自治体の助成制度を是非ご活用ください。多くの自治体で同様の制度が設けられています。
今回は、具体的な例として松戸市の制度をご紹介します。
【注意】 自治体によっては助成の内容や適用条件が異なります。松戸市以外の地域にお住まいの方は、この情報を参考に、必ずお住まいの市町村の障害福祉課にご確認ください。
松戸市:障害者住宅改修助成制度の詳細
松戸市では、重度障害児(者)の自立の促進および介護に適した福祉的な住宅改造に要する費用の一部を助成しています。
項目 詳細な内容
対象者 以下の全ての条件を満たす方です。 身体障害者手帳(1・2級)または療育手帳(A2以上)の交付を受けた方。 本人及び世帯の中心者が、松戸市に2年以上居住している方。 本人及び世帯の中心者が、市税を滞納していない方。 自宅(住民票上の住所)で生活している方。 ※65歳以上の方は、介護保険制度が優先適用されます。
助成額(上限額) 世帯の所得状況に応じて上限額が異なります。 市民税非課税世帯は30万円を限度とし、市民税課税世帯は15万円を限度とします。 ※介護保険制度と併用する場合は、助成額から介護保険の支給額を控除した額が対象となります。
対象となる工事内容(例) 障害者の心身状況・部位による不便さの解消・改善に応じた工事で、安全確保・介助者負担軽減に効果があるものです。具体的には、手すりの取り付け、段差の解消、スロープの設置、扉や便器の取替えなどが該当します。
申請方法・手続きの流れ 【最重要】必ず工事着工前に申請が必要です。 1. 助成の対象となるか、障害福祉課に確認・相談します。 2. 工事前申請(事前審査):申請書、住宅改修が必要な理由書、工事計画書(図面)、工事費見積書、工事前の写真などの書類を提出します。 3. 事前審査・決定通知:市からの通知を待って、工事に着工します。 4. 工事完了後申請:領収書、工事後の写真などを提出します。 5. 助成金の支給となります。
あなたの安心を、当事者であるアイズ ルームにお任せください。
アイズルーム代表の私も、視覚障害者1級の重度障害者であり、脊髄損傷による両足のしびれも抱えています。自らの経験からも、自宅の安全性が日々の生活、そして命に直結することを痛感しています。
私たちは、公的な助成制度を利用した改修工事を、単なる「仕事」として捉えるのではなく、障害当事者の「命と暮らしを守る社会貢献ビジネス」として真摯に取り組んでおります。
今回ご紹介した公的助成制度の活用は、
申請前の対象要件確認
医師や福祉専門職との連携(「理由書」作成)
複数の見積もりと助成対象工事の切り分け
工事着工前の厳格な事前申請手続き
など、複雑な知識と経験が必要です。特に工事着工前の事前申請は必須であり、手続きの不備で助成が受けられなくなるケースも少なくありません。
当社の修繕・リフォーム経験と、代表自身の障害当事者としての知見を活かし、お客様にとって最も安全で快適、かつ助成金を最大限に活用できる住宅改修プランをご提案させていただきます。公共機関や福祉住宅へのアドバイス実績も豊富です。
「公的助成制度を利用したいが、手続きが煩雑そうで不安だ」
「どのような改修が本当に必要なのか、当事者の目線でアドバイスが欲しい」
そうお考えの方は、ぜひアイズルームにご相談ください。制度利用から設計・施工まで、私たちアイズルームが一貫してサポートし、あなたの自宅を安心のバリアフリー空間へと変えます。
安全な住居は、全ての活動の基盤です。この機会に、未来の安心を手に入れるための第一歩を、経験豊富なアイズルームと一緒に踏み出しましょう。
まずはお気軽にご連絡ください。公的助成制度の利用可否を含めて、親身にご相談に応じます。
